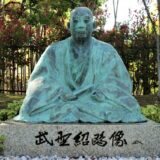こんにちは ヨハニです。 ※本ページはプロモーションを含みます。
今回は江戸時代の農民の主食『ひえ・あわ』について、ご紹介させていただきます。
そして、現在の生活に取り入れる事が出来るのかについても見ていきたいと思います。
1 江戸時代
そもそも農民とは農業を生業とする人の事をさします。
江戸時代の全人口の80%が農民だったそうです。農業で収穫したお米を年貢として納めて
いました。また、農民は勝手に農業をやめて田畑を手放すことはできなかったようです。
それは当時の領主の最大の収入が年貢にあったからでした。江戸時代の経済の中心が年貢で納められたお米でした。
領主からすると田畑を手放されて年貢が減ったら困りますからね。
2 江戸時代の農民の食生活
いきなり本題に入りますが。
農民は米を作っているのに、米作りを生業としているのに米を食べる事が出来ませんでした。
厳密に言えば特別な時にしか食べる事が許されていませんでした。例えば収穫時期などは許されていたようです。
というのも当時の統治機関である“幕府”から“農民は粗食を心がけるように。雑穀を作って食べるように。”といった内容のお触れがあったようです。
主に主食です。そこで本題。“ひえとあわ”です。
3 稗(ひえ)
日本では縄文時代の前期から栽培されていたお米と同じイネ科の植物です。明治時代まで主食用として栽培されていた地域もありました。畑でも水田でも栽培は可能です。食味は粘り気がなくパラパラとした食感だそうです。一言で言えば美味しくないという事でしょう。しかし、栄養価が高く、ミネラルや食物繊維が豊富。現在ではお米と混ぜて食べるなど人気だそうです。
現在では主食としては厳しそうですね。特に江戸時代では朝に一日分を一気に炊いていたので“美味しくなさ”はひとしおですね!
長所→栄養価が高い。長期保存が可能(アクが強いため虫がつきにくい)
短所→食味が悪い(まずい)。調理前にアク抜きが必要。
※オシャレなカフェのメニューにありそうですね。古代米みたいに……。
稗は田んぼに雑草として生える事があり今の農家の方にとっては迷惑な草の一種になっているようで…発生量が多いようです。
4 あわ
お米や稗と同じく、あわもイネ科です。五穀の一つに数えられます。
※五穀とは…内容は時代や地域で違ってきます。(え!そうなん?)
いわゆる『穀物』に含まれない、食べる事が出来ない“麻”なども含まれる事があります。
また、よく聞く『五穀豊穣』は穀物全般の総称として用いられます。
※五穀に含まれる代表的なもの
・発芽玄米
・麦
・古代米
・あわ
・きび
・豆
長所→米に比べると栄養価が高い。
短所→低カロリーで腹持ちが悪い。おいしくない。
短所を逆手に取り米粉に混ぜて胃に負担をかけないようにしたりもします。
あわの生産量は第二次世界大戦後に激減しました。かつてはお粥にして食べられていましたが
現在では家畜やペットのエサとしての方が需要が多いようです。
国内の主要産地;関東地方、東北地方、東海地方
5 まとめ
ネット通販で調べてみると稗はだいたいキロ2000円~3000円くらいしていますね。
最近お米が高くなったとはいえ、さすがにそこまで高くはありません💦
粟はキロ1000円くらいです。た、高い💦
安かったら試してみようと思ってましたが、ちょっと手が出ません。
これは需要と供給の関係でしょうか。消費者が求めなくなったからでしょうか。
確かに白米は美味しいですよね!私も玄米食を続けている時、たまに食べる白米をとてつもなく美味しく感じますので💦
そこでふと気づきました。こうやって昔の文化が廃れていくのかな?と。
でも、それが文化という事でしょうか?
……奥が深い!!

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。