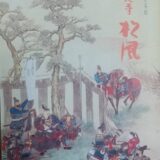こんにちは ヨハニです。 ※本ページはプロモーションを含みます。
少し前に大阪城の入館料が2025年春から2倍の1200円になるよ、というニュースがありました。今の大阪城は復興版の大阪城なのは皆さんご存じだとおもいますが、その前に3名の方が大坂城を建てていたという事をご存じでしょうか?大坂城の歴史を紐解いて魅力に迫りたいと思います。
1 今の天守閣は徳川家の大坂城
現在、大坂城として目にする建物は1931年に復興された『天守』です。博物館になっていて『大阪城天守閣』とされています。更に言いますと、目にすることの出来る櫓や石垣などは全て江戸時代のもので、いわゆる『徳川大坂城』です。徳川家が築城したお城です。今の天守閣は初層から4層までは徳川大坂城風の白漆喰壁で5層目は豊臣大坂城風の黒漆に金箔で虎のレリーフや鶴の絵が描かれています。逆にいうと豊臣大坂城の天守閣は黒かったんです。
☆歴史的ハッスルポイント①☆
大坂夏の陣に勝った徳川方は豊臣秀吉が築城した大坂城を地中に埋め、その上に新たに城を築城したようです。これが徳川大坂城です。
徳川大坂城は建て直す事で徳川の威信を知らしめる為であったと言われています。ですので、今でも水道工事などで穴を掘ると豊臣大坂城の遺構が出てくるようです。
☆歴史的ハッスルポイント②☆
2倍に値上げ。大阪城天守閣入館料が2025年春から1200円に値上げになります。現在は600円です。中学生以下は無料です。その理由がまさに豊臣秀吉が築いた初代大坂城(豊臣大坂城)の石垣を展示する新しい施設のオープン。そして将来の補修工事などを見据えての事だそうです。
結論を言いますと今の大阪城の天守は徳川大坂城の天守台石垣の上に作られ、資料の乏しい豊臣大坂城の天守閣を想像し大阪夏の陣図屏風絵などを参考に模擬復興された創作物です。豊臣秀吉が築城した大坂城の復刻版ではないという事です。すみません。徳川大坂城より豊臣大坂城の方に勝手に愛着を持ってしまうのは私が関西人だからかもしれません💦見たいですよね!豊臣大坂城!!来年の春には豊臣大坂城の石垣(一部)を見る事が出来るようなので期待できますね!
徳川大坂城
総責任者は藤堂高虎。天下普請(江戸幕府が全国の諸大名に命令し、行わせた土木工事)。以前の豊臣大坂城は時代的に古い城であったので新たな城郭技術で建てられました。9年間。城郭面積は豊臣大坂城の1/4。天守は高さ・総床面積とも豊臣大坂城を超える規模のものが築かれました。豊臣大坂城と徳川大坂城のどちらが大きいかは一概には言えないようですね。
2 豊臣秀吉が築いた大坂城
豊臣大坂城
初代築城総奉行、黒田孝高が縄張を担当。

縄張とは本丸や二の丸・三の丸などの配置や堀・土塁なども含めた城の全体像を設計する事です。
大坂の市街から天守がよく見えるよう天守の位置、街路などを工夫したそうです。石垣の構築方法は安土城から踏襲しており、現在の大阪城の地下7メートルから当時の石垣が発見されています。(これが2025年から展示されるのでは!?)
☆歴史的ハッスルポイント③☆
豊臣大坂城の防衛上最大の弱点は南側にありました。大坂冬の陣でよく耳にする出城・真田丸はこうした弱点に対する策として作られました。
豊臣大坂城は落城の際に石垣と堀も破壊されている事から当時の遺構はほぼ残されていなく、琵琶湖に浮かぶ竹生島にある宝厳寺唐門(国宝)が豊臣大坂城の唯一の遺構ではないかと言われています。
3 初代大坂城はお寺!? お坊さんが城主!?
豊臣秀吉が大坂城を築城する前には大きなお寺がありました。その名も『石山本願寺』。お寺と言っても堀や塀、土居などがあり要害を強固にし武装を固めて防備力を増していたのでほとんど『城』でした。本願寺教団の本山でした。各地で支持をうけて戦国時代においては一大勢力となっていました。一向一揆などがそうです。豊臣秀吉以前の為政者である織田信長と敵対することになり、ここ大坂の地においても抗争することになりました。(石山合戦)
☆歴史的ハッスルポイント④☆
『石山』と呼ばれるようになった理由は諸説あり明確にはなっていません。一説には礎石に使える大きな石が土中に多数揃っていたという不思議な状況から呼称されたと言われています。
この石山合戦において織田信長は大坂の周辺に10ヵ所の付城を築城しました。尼崎城・大和田城・吹田城・高槻城・茨木城・多田城・能勢城・三田城・花隈城・有岡城です。この戦いは結局、正親町天皇の勅令により双方の和議が成立しました。織田軍の長期の攻撃にもかかわらず武力で開城される事はなかったという事です。それだけ石山本願寺の城郭そのものが難攻不落の名城であったという事です。
しかし、和議後の石山本願寺の明け渡しはスムーズには進みませんでした。和議後に本願寺宗主の本願寺顕如が退去しました。しかし、最後に顕如の長男である教如が退去した直後に堂舎・寺内町が炎上し灰となりました。二日一夜炎上し続けたと伝わっています。その後に豊臣秀吉が大坂城を築城したので大坂本願寺の規模や構造などはほとんどわからなくなってしまいました。
4 まとめ
こうして見てみると大坂の地がいかに要衝の地であったかが見てとれます。現在よりも陸地が少なく大阪湾が近くにあり、川の本数も多かった戦国時代。交通手段・輸送手段の有力な一つとしての船運。様々な利点が働いた地と言えるでしょう。また、その川などを利用した城の天然の防備。一説には豊臣秀吉の大坂城の構想は実話、織田信長から引き継いだのではないかと言われています。織田信長も大坂の地の利点に気づいた一人だったのでしょう。特に織田信長・豊臣秀吉に象徴される有力戦国武将は農耕による経済から商業(貿易)による経済にシフトチェンジしていたところを考えても頷けるのではないでしょうか。商売と言えば大阪。商人の街・大阪。これは地形と歴史から考えると自然だと思えますね。
☆歴史的ハッスルポイント⑤☆
初代:石山本願寺
2代目:豊臣大坂城
3代目:徳川大坂城
4代目:昭和大阪城
………という事でしょうか💦
やっぱり、歴史は良いでね。その地の歴史を紐解いていくと、その地域の特性と魅力がわかってくる。地形と歴史によってその地域の特性が生まれ育っていく。
大阪の特性を少しでもお伝え出来たでしょうか?大阪城だけでなく、大阪にお立ち寄りの際は『商人の街・大阪』を楽しんでみてはいかがでしょうか。私は早く豊臣大坂城の石垣が見たいです!!

最後までお付き合いいただきありがとうございました。少しでも大阪の魅力を発信できていましたら、嬉しいです。


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ace9831.1c718721.3ace9832.f212949c/?me_id=1263613&item_id=10003251&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-ningyohonpo%2Fcabinet%2Fgogatu%2Fnew5premomini-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ace9e60.cd0a9714.3ace9e61.6413673d/?me_id=1311340&item_id=10001394&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkeepon%2Fcabinet%2F04355431%2F04430687%2F4571350470325na.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3aceb9f5.cafc2977.3aceb9f6.867205a5/?me_id=1369688&item_id=10000086&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsnailshop%2Fcabinet%2Fdvdsakuhin%2Fisiyama.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3acec1d7.7622a1ae.3acec1d8.154186d3/?me_id=1297418&item_id=10000149&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsowxp%2Fcabinet%2Ftravel%2Ftravel_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3acec31c.76bd334d.3acec31d.d9e5dd9f/?me_id=1382162&item_id=10000053&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkatuuya2012%2Fcabinet%2Fcompass1582080725.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)